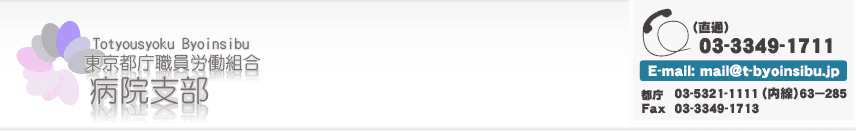

「神経内科病棟ではたらく6年目の看護師です。4年目くらいから疲れたときに腰が痛むようになり、最近は整体に定期的に通わないと身体が持ちません。まだ20代なので、腰痛は看護業務が原因だと思います。これは労災にならないのでしょうか?整体の費用もばかになりません。」
「私の場合は、仕事中にコードをひっかけてテプラを足に落として右足の小指を骨折してしまいました。労災だと思ったのですが「あなたの不注意でしょ」と言われてしまいました。自分にミスがあったときは労災にならないのでしょうか?」
![]()
なるほど、それはきついですね。
最初のケースについて、労災になると私は考えます。
労働基準監督署の判断では、労災と認められるケースもあるでしょうし、認められないケースもあるでしょうが、これは労災となるようにしていかなければならないと考えます。
二番目のケースについて、労働者の不注意だけを理由として労災保険を受給できない、ということはありません。
まずは、労災という制度と考え方から説明します。
労働災害(労災)とは、労働者が業務中、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことをいいます。
労災に対しては、労働者災害補償保険法(労災保険法)によって、労災だと認定されれば、国から、現物(医療)と現金の保険給付を受けることができます。
これは、労働者とその家族の生活を保障するため、使用者の過失や資力(支払い能力)を問題にせず、簡易に、迅速に、定額の補償を受けられることとした、社会制度です。
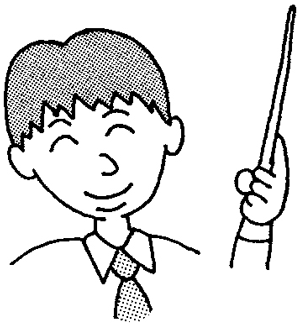
ですから、労災保険を受給できれば、医療費の心配なく、治癒に至るまで通院を継続でき、また、これによって休業することになった場合、その期間の休業補償も受給できます。
「簡易迅速定額」というところがミソでして、平均賃金さえ計算できれば労災によって具体的にいくらの損害が出ているとか、怪我や病気の発生について誰にどんな責任があるかとか、そういうことは一切関係がない。
「仕事による怪我や病気」といえさえすればよい、ということになるわけです。
また、以上の労災保険は、民間の事業所に勤務する労働者の場合です(もともと自治体等の公共の職場から民間に委託された事業所で民間の事業主に雇用された形の労働者も含む。)。
公務員の場合には、公務員用の災害補償制度が別に用意されていますのでそちらで手続きすることになりますが、考え方や実務の取り扱いなど、ほぼ民間の場合と同様です。
実務的な手続きについてです。
労働災害を認めてもらおうと考えた被災者は、まず、事業所を管轄する労働基準監督署に請求をしなければなりません。
労基署には、請求書の書面がありますから、その書面をもらってきて書き込んで提出すればよいです。
この場合、事業主の署名欄、休業の場合には医師の証明欄があり、よくそのことが問題になります。
ただ、事業主の署名欄は、事業主に協力してもらえない場合、事業主の署名欄が空欄であっても請求することは可能です。
医師の場合には、協力を要請することが必要になります。
労基署では、当該の怪我や病気が、「業務上」発生したものであると認めれば、支給決定を行うことになります。
そこで問題となるのが、いかなる場合が「業務上」発生したものであると認定されるか、です。
この「業務上」には、その要素として、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要素に基づいて判断されるとされています。
「業務遂行性」とは、「事業主の支配ないし管理下にあるなかで」という意味です。
ですから、例えば、仕事で移動中に自転車でぶつかってこられて怪我をした場合と、休憩中に昼食を食べに外出し、その帰りに自転車でぶつかってこられて怪我をした場合とで、後者の場合には、「業務遂行性」がないと考えられるというわけです。
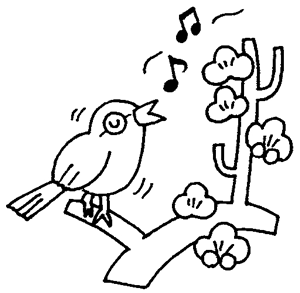
次に、「業務起因性」です。
これは、当該の病気や怪我が、業務の遂行によって発生したといえる関係、つまり仕事と病気・怪我の因果関係が問題になるというものです。
実務でよく問題になるのは実はこの論点であり、第一の事例の場合も、実はこの点がもっとも問題です。
つまり、第一のケースの場合、腰痛も、真実看護業務が原因であるといえるかどうかが問題だ、というように労基署は考えるわけです。
例えば、看護師として業務に就く前に、あなたには腰に負担のかかる別の仕事や、スポーツなどを行っていたことはないか。
仕事以外で、腰に負担のかかる、例えば高齢者の家族の介護などをしたことはないか。
こんなことを検討しながら、看護の業務以外に原因があるとは考えられないのか、というところまで絞り込もうとするわけです。
しかし、この点は二重の意味で不当な態度であり、看護業務の場合当然「業務起因性」がある、と考えるべきです。
第一に、外に原因を探していれば、業務以外に腰痛と無縁であったと断言できる人はまずいないのであり、そういうことを言い出していればおよそ労災を認めないことにしかならないからです。
通常の人は健康体で業務に従事し始めたと考えるべきであり、そうでない人は医療記録の存在などから明白にそうでないと考えられる場合に限るべきです。
第二に、それを前提に、遂行している業務の実態から、当該症状が発生する蓋然性がどれくらいあるかで考えるべきです。
この点、腰痛の場合、「重すぎる、負担がかかりすぎる、といった強度の身体的負荷」「立位などの長時間の姿勢拘束」「前屈やしゃがみなどの不良姿勢」が原因として考えられるところです。
看護業務の実態からすれば、患者の身体を抱える、支えるといった作業からの強度の身体的負荷や、立位、しゃがみといった実態は当然存在しているでしょう。
労働省(当時)は、1994年に「職場における腰痛予防対策指針」(基発547号)を発表し、その中で、作業管理、作業環境管理、健康管理および労働衛生教育について指示しています。要するに腰痛を起こさないように業務の仕方や姿勢、時間を職場がきちんと管理せよ、ということです。
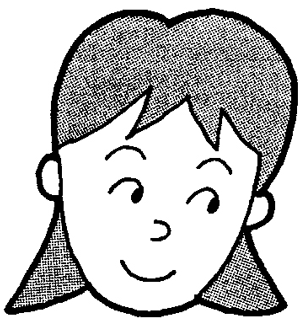
これを具体化することを考えたとき、中央労働災害防止協会の資料は参考になります。
これによれば、職場における常時人力のみの場合、男性は体重の40%以下に持ち上げを押さえる、ということが言われています。
女性の場合であれば、持ち上げ能力は男性の60%ぐらいとされているので、女性は体重の24%以下までということになります。50キログラムの女性の場合では、12キログラムまで、ということになるわけです。
こうした重さを遙かに超えた持ち上げに従事しているなど、強度に身体的負荷のかかる看護業務の場合、「業務起因性」が認められて当たり前です。
むしろ、労基署は、「職場における腰痛予防対策指針」の定めをどれくらいその職場が実践しているかを調査し、その実践が不十分であれば業務起因性は当然推定される、くらいの発想でのぞむべきものと考えます。
いずれにせよ以上の内容の調査をすることになるので、実際上の労災保険の受給は、労災保険の趣旨の「簡易迅速」という部分は、残念ながらなかなかそのとおりにはいっていないというのが実際のところです。
あと一点、実務的な問題で言うと、「整体」の問題があります。
「整体」については、これが「治療」なのか、という点で問題が残るものです。
その点の争いをなくすためには、「整体」に行く必要性があるということを医師の診断・指示に基づくという形で明らかにすると良いでしょう。
「あなたの不注意」が問題になっている第二のケースについては、上記の通り、労災は、事業主の過失の存否を問題にせず、「業務上」といえるか否かだけを問題にして支給決定を検討する制度です。
事業主の過失が問題にならないように、あなた、つまり労働者の過失の存否も問題にはなりません。
参考になる判例として、福岡高裁平成5年4月28日判決(労働判例648号82頁)があります。
これは出張中の宿泊施設で酔って階段から転倒した事故について、「業務上」を認定した事例です。
これから考えても、「仕事中にコードをひっかけてテプラを足に落として右足の小指を骨折した」という状況であれば、あなたがミスをしたということを理由に「業務上」が否定されるということはないと考えられます。
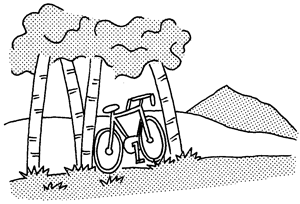
労災を引き起こさないためようにするには、使用者の安全配慮義務を果たさせることが重要です。
上記の「職場における腰痛予防対策指針」も、結局は、この義務の具体化の一つと考えることができます。
安全配慮義務とは、公務員の場合でも、民間の場合でも、使用者に課せられる義務です。
民間の場合は、労働契約法第5条という法律に基づいています。
これは、労働者の生命、身体、心身の安全等をはかるため、使用者がなし得る具体的な措置を取らなければならない、とするものです。
ここで言う「なし得る具体的な措置」とは、一律なものではなく、使用者にとって比較的ハードルの低いもので、その職場にとって、あるいはその労働者に対して必要と考えられる措置を言います。
例としては、職場の配置であったり、人数であったり、その人の労働時間の増減であったり、使用させる用具・服装であったり、研修であったり、です。
「テプラをひっかける」というようなことが今後起こらないようにするためにはどうしたらいいか。
また、みなさんにとっては職業病といえる「腰痛」を起こさないようにするためにはどのような仕事の仕方であったり人の割り振りであったりすればよいのか。
ぜひ、この観点で使用者が行わなければならないことを明らかにすると共に、現場で労働者が気をつけるべきことも明らかにする。
そういう職場での討議や、使用者との交渉を心がけて頂ければと考えます。
以 上